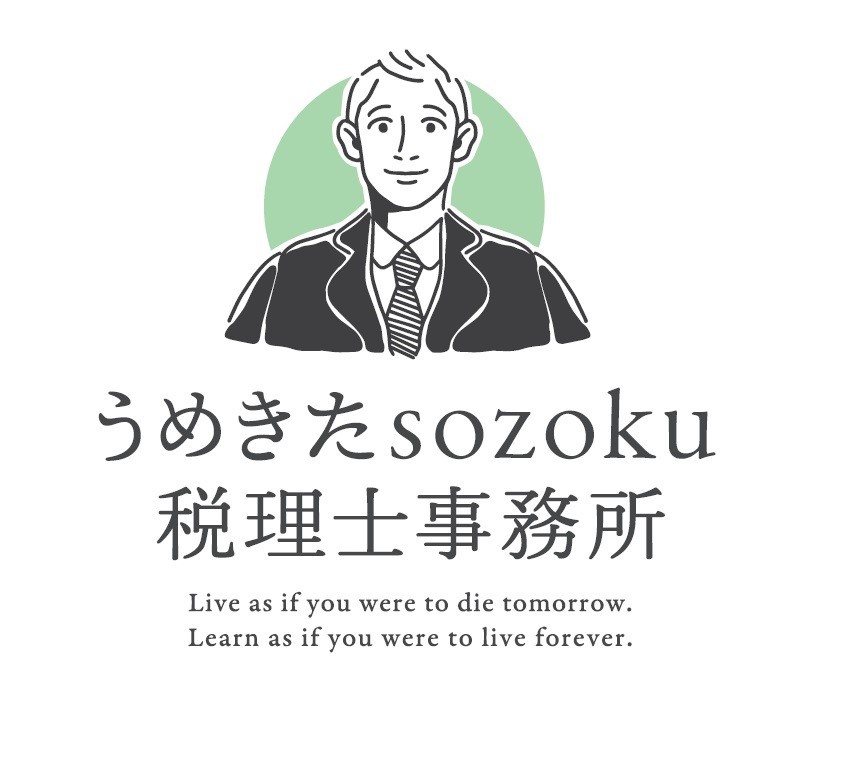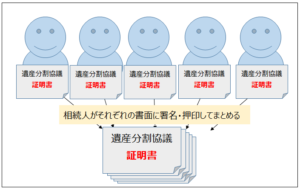【税制改正】教育資金贈与信託の使い方にちょっと待った!23歳以上に厳しく、3年内贈与加算の対象にもなるかも。
目次
教育資金贈与信託とは?
2018年9月末時点の実績で、
契約件数:20万件 超
信託財産設定金額:1兆4,000億円 超
(参考:税制改正資料より)
となっているそうです。
かなりの件数と金額ですね。
ただし、今回の税制改正では2021年3月末まで延長されるとともに、要件がすこし厳しくなりました。
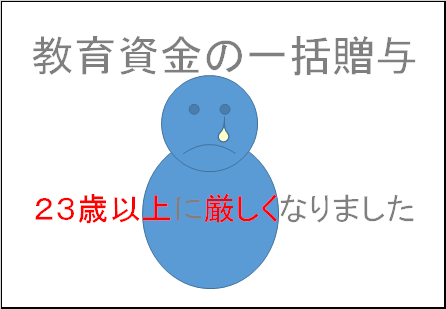
制度の概要
- 親・祖父母から子・孫・ひ孫への教育資金の贈与
- 1,500万円まで一括贈与しても贈与税が非課税
- もらう人名義の信託口座が必要
- 2021年3月31日まで(改正で延長)
- あげた人が亡くなっても残額が(原則)相続財産にならない(税制改正で制限あり)
税制改正の内容
①もらう人が儲けてたらダメ(所得1,000万円までの制限)
教育資金をもらう人に所得制限がかかります。
あげる人の所得制限ではないです。そもそも所得が高く貯蓄のある方からの早期の財産移転が趣旨なので。
もらう人の昨年の年収が1,000万円を超えている場合は、贈与税の非課税措置の対象外となりました。
小学生でも人気youtuberになったとか、大学生でIT関連の会社を起業して儲かっちゃった、などの場合は注意が必要になります。
その時はこうしましょう
この場合に信託財産に一括でお金を入れると贈与税が掛かることになります。
ですので、必要な教育資金があれば、直接その都度払ってあげるようにしましょう。
教育資金を必要な時にその都度払うのは、贈与税の対象になりません。
どれだけ掛かっても非課税になります。
②3年内贈与加算の対象になることも
あげた人の亡くなる前3年内の贈与については、もらった人が以下の場合を除いて、亡くなった時の管理残高を相続財産に加算します
となりました。
3年内贈与加算については、こちらの記事も読んでみてください。
相続開始前3年内でも問題なし!節税できる暦年贈与の方法を解説
要件
その要件とはあげた人が亡くなった日のもらった人の状況が、
- 23才未満
- 学校に通っている
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている
のいずれかに該当していれば、相続財産には加算されません。
要するに、
「亡くなる直前に23才以上で働いている孫に対しての駆込み贈与をして、ムリくり相続税を下げようとするのは止めてね。」
となったわけです。
そりゃそうですね。
管理残額って何
・教育資金の贈与の全額が亡くなる3年以内の場合
⇒ 残高の全てが相続財産
・亡くなる3年前より昔からこの制度を使って贈与をしていて、何回かに分けて贈与を行っている場合
⇒ 残高のうち3年内贈与分が相続財産
となります。
その時の残高がそのまま相続財産になるわけではありません。それではあんまりです。
というわけで、
3年内に贈与した金額に対応した残高=管理残高
が相続財産の3年内加算の対象になります。
③23歳以上には厳しくなりました
23歳を区切りにして教育資金の範囲が厳しくなります。
- 学校に支払われる費用
- 学校に関連する費用
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講するための費用
に対するものだけに限られることとなりました。
具体的には、
×(ダメ) 学習塾、そろばん教室、スポーツや文化芸術の習い事
のイメージです。
さすがに23歳超えてれば、まあいい大人ですからね。
学校関連などの教育資金はともかく、ピアノ教室代とかそこまですねをかじるのは如何なものか、ということでしょう。
たいていは孫への遺贈で2割加算
この制度はほとんどの場合、おじい様からお孫さんへの贈与になります。
相続財産になる場合は、通常は相続人でない孫に対して遺贈したものとみなされ相続税の2割加算の対象にもなってしまいます。
いつから?
①所得制限と②相続財産加算
2019年4月以降の贈与分からが対象になります。
2019年3月31日以前の贈与であれば、亡くなる3年以内のものであっても相続財産に足し戻されることはありません。
③23歳以上の教育資金の範囲
2019年7月以降に支払われる分からが対象になります。
相続税申告をする際の税理士さんの注意点
孫への遺贈の相続財産が漏れてた!なんて後から税務署から指摘された日には、相当凹みます。
お客さまにもご迷惑になりますし、最悪、ミスとして賠償責任を取らされることも・・・><
とにかく絶対に避けなければいけない事態です。
そのためには、相続人に対し初回面談時に教育資金贈与信託の有無をしっかりと確認しておくようにしましょう。
わたしも自作のチェックリストに、税制改正のたびに項目を加えたりしています。
それと、やはり預金通帳のチェックは欠かせない!と思います。
あわせて読んでみて下さい。
預金通帳をしっかり見ない税理士はダメ!税務署も100%見ます。
この記事を書いたひと

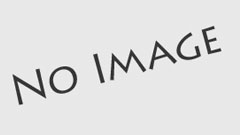 事務所運営2023年2月1日事務員さん募集します 時給1,400円~
事務所運営2023年2月1日事務員さん募集します 時給1,400円~ 事務所運営2021年1月21日独立して2年6か月が経過しました。独立2年目を振り返ってみます。
事務所運営2021年1月21日独立して2年6か月が経過しました。独立2年目を振り返ってみます。 相続税2021年1月6日【遺産相続冒険譚】ティティの奇妙な冒険 ~矜持と高楊枝~ 第12話
相続税2021年1月6日【遺産相続冒険譚】ティティの奇妙な冒険 ~矜持と高楊枝~ 第12話 事務所運営2020年12月22日【ふたたびリモートワークのお知らせ:2021年1月5日まで】大阪府コロナ警戒警報に伴う当事務所の対応
事務所運営2020年12月22日【ふたたびリモートワークのお知らせ:2021年1月5日まで】大阪府コロナ警戒警報に伴う当事務所の対応