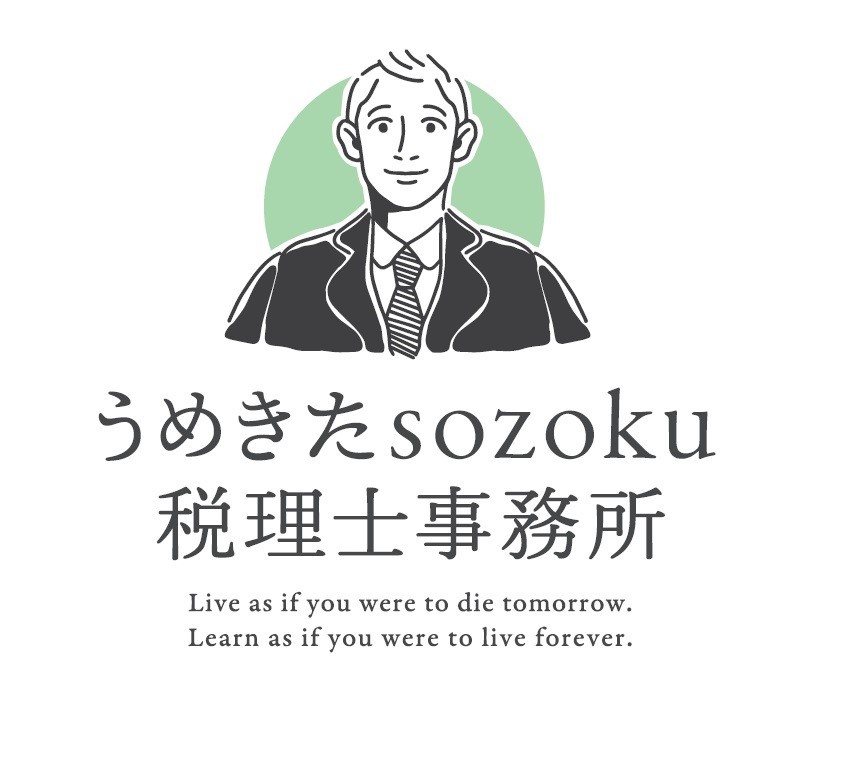相続税が掛かるか微妙な人は・・・。
相続税には遺産に係る「基礎控除額」という基準額があり、財産がこの基準額以下の人には相続税がかかりません。
-
目次
基礎控除の金額
基礎控除額は以下のように定められています。
※平成27年1月1日以後の相続・遺贈
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、平成30年に夫が亡くなり、妻と子ども2人が法定相続人の場合は、
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
となり、4,800万円以下の財産であれば、相続税は掛かりません。
-
基礎控除のボーダーラインの人は
ですが、実際にご自分でザッと計算してみて、この金額前後であった場合はどうすれば良いのでしょうか。相続税の申告期限は10ヶ月以内に行わなければならず、もやもやとした日々を過ごされる方も少なくないかと思われます。
その様な時は以下のような方法が考えられます。
①税務署に相談に行く
②税理士に相談に行く
③放っておく
①税務署に相談に行く
税務署は納税者からの質問にも広く対応しており、お近くの税務署に伺うと、一般的なことであればその場で教えてもらうことが出来ます。
もちろん費用はかかりません。税務署は怖いというイメージはありますが、割と紳士的で丁寧に対応してもらえることが多いようです。
ですが、基本的には納税させるための原則どおりの申告書を作る傾向にあり、こう申告すれば税金が安くなりますよ、といった内容については一切触れてくれないものと思ったほうが良いでしょう。評価の幅が広い不動産の評価方法についても、最も簡便的で高い評価額となる可能性が高いです。
そのため、大きな節税が可能な小規模宅地等の特例なども適切に申告してくれない可能性があります。しかも、この税制は当初申告要件(最初に出した申告内容が正しいとする要件)のものなので、税務署主導でも申告書が出されてしまった後ではやり直すのは非常に難しいでしょう。
結果的に納税額が高くつく、そもそも適切に評価すれば相続税の申告すら必要なかったかも知れないにも係わらず相続税の申告書を出してしまう、などということも考えられます。
②税理士に相談に行く
特に相続税に強い税理士であれば最も納税者の有利になるような評価をしたうえで、的確なアドバイスをすることが可能です。
不動産の評価方法についても、しっかりと現地を確認し、出来るだけ低い評価額になるように計算し、小規模宅地等の特例についても、節税策を踏まえた選択や、2次相続まで考えた上での納税計画を示すことが出来るでしょう。
それらを総合的に勘案した上で、実際に基礎控除以下なのかどうかをはっきりとさせることが出来ます。
試算や申告についての税理士費用は発生いたしますが、納税のトータルコストとしては安くなりますので、パフォーマンスに見合うものが得られるでしょう。
③放っておく
そのままにしておいても何も起こらないかも知れませんが、当然ながらそうでないケースもあります。
相続税の申告期限を過ぎても何も税務署から言ってこないのでホッとしていたら、ある日突然電話が、、、なんてことはままあることです。その場合は延滞税に無申告加算税など通常であれば掛からない税金がペナルティで課されることもあります。しかも相続税の調査等は通常相続開始後3年か4年後に行われることもあり、いつ調査対象になるかは税務署職員以外には解らないのです。
よほどの精神力でその期間を待てるのであれば良いですが、そうしたことがストレスに感じられるようであれば、税務署か税理士かのどちらかに相談に行かれるのが良いでしょう。
この記事を書いたひと

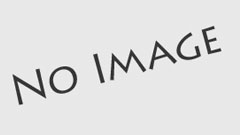 事務所運営2023年2月1日事務員さん募集します 時給1,400円~
事務所運営2023年2月1日事務員さん募集します 時給1,400円~ 事務所運営2021年1月21日独立して2年6か月が経過しました。独立2年目を振り返ってみます。
事務所運営2021年1月21日独立して2年6か月が経過しました。独立2年目を振り返ってみます。 相続税2021年1月6日【遺産相続冒険譚】ティティの奇妙な冒険 ~矜持と高楊枝~ 第12話
相続税2021年1月6日【遺産相続冒険譚】ティティの奇妙な冒険 ~矜持と高楊枝~ 第12話 事務所運営2020年12月22日【ふたたびリモートワークのお知らせ:2021年1月5日まで】大阪府コロナ警戒警報に伴う当事務所の対応
事務所運営2020年12月22日【ふたたびリモートワークのお知らせ:2021年1月5日まで】大阪府コロナ警戒警報に伴う当事務所の対応